非化石証書とは?|再エネ調達と脱炭素経営に役立つ制度を徹底解説
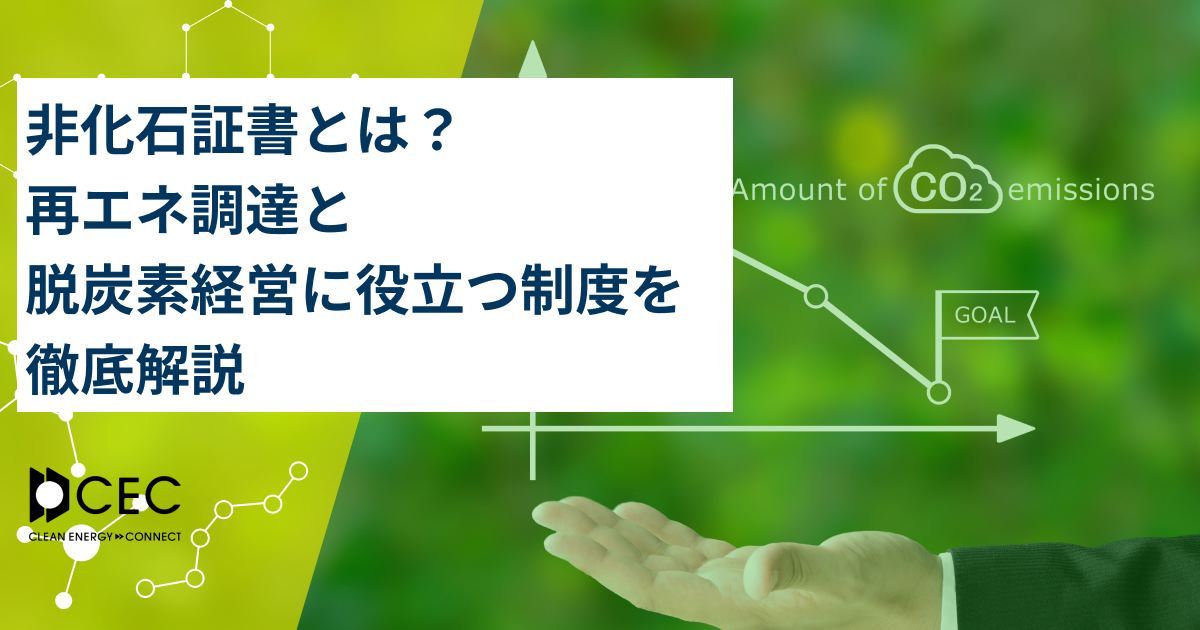
気候変動対策や脱炭素社会の実現に向け、再生可能エネルギーの利用はますます重要性を増しています。その中で、電力の「環境価値」を客観的に証明する制度として注目されているのが「非化石証書」です。非化石証書は、太陽光、風力、地熱、バイオマスなどの再生可能エネルギーに加え、原子力発電、大型水力といった化石燃料を使用しない非化石電源から得られる電力の環境価値を「証書」という形で担保する仕組みです。
本記事では、非化石証書の基本的な仕組みや種類、取引の現状と課題、さらに今後の制度改正や市場動向について解説します。経営戦略やESG対応においても注目度が高まるこの制度の意義を、わかりやすく整理してお伝えします。
目次
非化石証書の基本概要

非化石証書とは?
非化石証書は、化石燃料を用いずに発電した電力の「環境価値」を証明するために発行される証書です。対象となるのは、太陽光・風力・地熱・バイオマス・水力といった再生可能エネルギーに加え、原子力発電なども含む「非化石電源」です。発電設備が固定価格買取制度(FIT)の認定を受けている場合は「FIT非化石証書」となり、FIT対象外の電源については「非FIT非化石証書」として発行されます。
これにより、企業や小売電気事業者は、自社が利用する電力が非化石電源由来であることを証明でき、消費者への環境訴求やESG(環境・社会・ガバナンス)活動の一環として活用することが可能です。
制度の背景と目的
世界各国で化石燃料の削減と脱炭素化が急務となる中、再生可能エネルギーやその他の非化石電源の導入が進む一方で、その環境価値をどのように評価・活用するかが課題となっていました。非化石証書は、こうした電源が実際に温室効果ガスの排出削減に貢献していることを客観的に数値化・証明する仕組みであり、再エネ普及や非化石電源利用のインセンティブを高める役割を果たしています。
また、証書を通じた取引市場の形成により、電力の環境価値を透明かつ公正に流通させることが可能となり、電力システム全体の効率化や市場の健全な発展にも寄与しています。
非化石証書の種類とその特徴

非化石証書は、大きく分けて 「FIT非化石証書」 と 「非FIT非化石証書」 の2種類があります。さらに「非FIT非化石証書」には 「再エネ指定あり」 と 「再エネ指定なし」 があり、それぞれ取引条件や利用用途が異なります。
非化石証書の種類と概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 証書の種類 | FIT非化石証書/非FIT非化石証書(再エネ指定あり/なし) |
| 対象発電設備 | FIT対象:太陽光、風力、中小水力、地熱、バイオマス 非FIT対象:「再エネ指定あり」大型水力、卒FIT設備など 「再エネ指定なし」原子力、廃プラスチック、水素、アンモニア等 |
| 取引方法 | 市場取引(JEPX・年4回入札)、または相対取引(非FIT証書のみ)。 FIT非化石証書は市場取引に限定。 |
| 価格帯 | FIT: 最低0.4円/kWh~最高4.0円/kWh 非FIT(再エネ指定あり): 0.6円/kWh〜1.3円/kWh (※2024年度時年度オークション実績) |
証書の種類ごとに「環境価値の訴求内容」や「取引価格の安定性」が異なるため、企業や小売電気事業者は自社の調達方針や顧客への提供メニューに応じて、最適な証書を選択することが重要です。特に「再エネ指定あり」の証書は、国際的なイニシアティブ(RE100やCDP報告など)でも再生可能エネルギー利用として認められるケースが多いため、企業の脱炭素経営において意義が大きいと言えます。
非化石証書の取引制度と流れ

市場取引と相対取引の仕組み
非化石証書の取引は、大きく 「市場取引」 と 「相対取引」 の2つに分けられます。
- 市場取引:日本卸電力取引所(JEPX)で年4回実施される入札方式が中心です。国が最低・最高価格を設定しているため、現時点では発電方式や設備特性ごとの価格差は反映されにくい仕組みとなっています。
- 相対取引:発電事業者と小売電気事業者、または条件を満たす需要家が直接契約を結ぶ形態です。利用できるのは 非FIT非化石証書 に限られます。相対取引は柔軟性が高く、需要家の環境戦略に合わせた調達を可能にする点が特徴です。
今後の制度改正やシステム高度化により、発電方式や供給特性を反映した自由度の高い価格形成が可能になることが期待されています。
トラッキング情報と権利確定のプロセス
非化石証書には、発電設備区分、設置地域、運転開始日などを含む 複数の属性情報(トラッキング情報) が付与されます。これにより、証書の環境価値や「追加性(新規性)」を確認でき、利用者にとって信頼性の高いエビデンスとなります。
さらに、証書は 権利確定手続き を経ることで二重利用を防止します。具体的には、証書を取得した小売電気事業者や需要家が権利の確定申請を行い、使用済みの証書は「リタイア処理」され、再利用できなくなります。この仕組みにより、実際に供給された電力が再生可能エネルギー由来であることを確実に証明することが可能です。
非化石証書が担う環境価値とそのメリット

再生可能エネルギーの普及が進む中で、非化石証書はその環境価値を「見える化」する仕組みとして重要な役割を果たしています。企業や自治体は証書を活用することで、自らのエネルギー利用が環境負荷低減につながっていることを客観的に示すことができます。
以下に、非化石証書がもたらす主なメリットを整理します。
非化石証書の主なメリット
①環境価値の証明
使用電力が再生可能エネルギー由来であることを第三者に証明できる。
ESG投資の評価やサステナビリティ報告書での開示に活用可能で、企業ブランドの向上に直結する。
②脱炭素推進への貢献
企業のScope2排出削減に直接寄与し、温室効果ガス削減目標の達成に貢献する。
サプライヤーや取引先にも同様の取り組みを促すことで、バリューチェーン全体の脱炭素化を間接的に後押しできる。電力調達を通じて気候変動対策への積極的な姿勢を示すことが可能。
③市場の透明性向上
トラッキング情報により、発電源・地域・運転開始日などが明確に管理される。
市場取引を通じて環境価値に公正な価格がつくことで、再エネ投資のインセンティブとなる。
④企業の競争優位性確保
非化石証書の取得は先進的な環境経営の証となり、競合との差別化につながる。
顧客・投資家・取引先からの信頼を高め、調達や投資判断における優位性を確保できる。
非化石証書の課題制度改革の方向性

非化石証書は再エネの環境価値を「見える化」する重要な制度ですが、現行の仕組みにはいくつかの課題も残されています。
現状の課題
- 市場取引の制約:入札回数が年4回に限られており、取引の自由度が低い。国が設定する価格レンジ内でしか取引が成立しないため、発電設備ごとの特性や環境価値が十分に価格に反映されにくい。
- 価格差評価の不足:発電方式や設備性能の違いによる価値が現状では十分に評価されず、技術革新や効率改善が価格に結び付きにくい。
- 対象者の制限:非化石証書を購入できる主体は市場ごとに制限されており、制度運用や行政手続きの柔軟性が不足している。
制度改革の方向性
政府および関係機関は制度改善を進めており、以下の変化が期待されています。
- トラッキング機能の高度化:デジタル技術を活用した詳細な属性管理や帳簿整備により、証書の透明性・信頼性が強化される。
- 国際基準との整合性:欧米やアジア各国でも同様の制度が広がっており、将来的には国境を越えた環境価値取引市場の形成が見込まれる。
これらの改善が進むことで、非化石証書は単なる制度にとどまらず、 企業の調達戦略や投資判断を左右する重要な仕組み へと進化していくでしょう。結果として、国内外での再エネ評価の統一や市場の拡大が進み、クリーンエネルギー利用の加速につながることが期待されます。
まとめと今後の展望

非化石証書は、環境価値の証明にとどまらず、企業が脱炭素社会に向けた責任ある行動を示すための戦略的ツールとなっています。証書を活用することで、自社の再エネ利用を客観的に証明でき、投資家・顧客・従業員を含むステークホルダーに対して「持続可能な経営姿勢」を明確に打ち出すことが可能です。これは、単なる環境対応を超え、企業価値向上やリスクマネジメントの観点からも大きな意味を持ちます。
現行制度には、市場の自由度や価格形成の精緻さといった課題が残るものの、2026年度に予定される日本卸電力取引所(JEPX)のシステム更新やデジタル技術によるトラッキング高度化により、透明性と柔軟性が飛躍的に向上する見込みです。これにより、経営判断に資する正確で信頼性の高い環境価値データを得やすくなり、脱炭素戦略の実効性を高める基盤が整いつつあります。
今後の企業経営においては、非化石証書を単なる制度対応として捉えるのではなく、事業継続性や市場競争力を確保するための「戦略投資」として位置づけることが重要です。早期に取り組むことで、規制強化や市場変化に先んじた競争優位を築き、持続可能な成長へとつなげることができるでしょう。






