RE100時代の経営戦略|再生可能エネルギー調達と脱炭素経営の実践ガイド
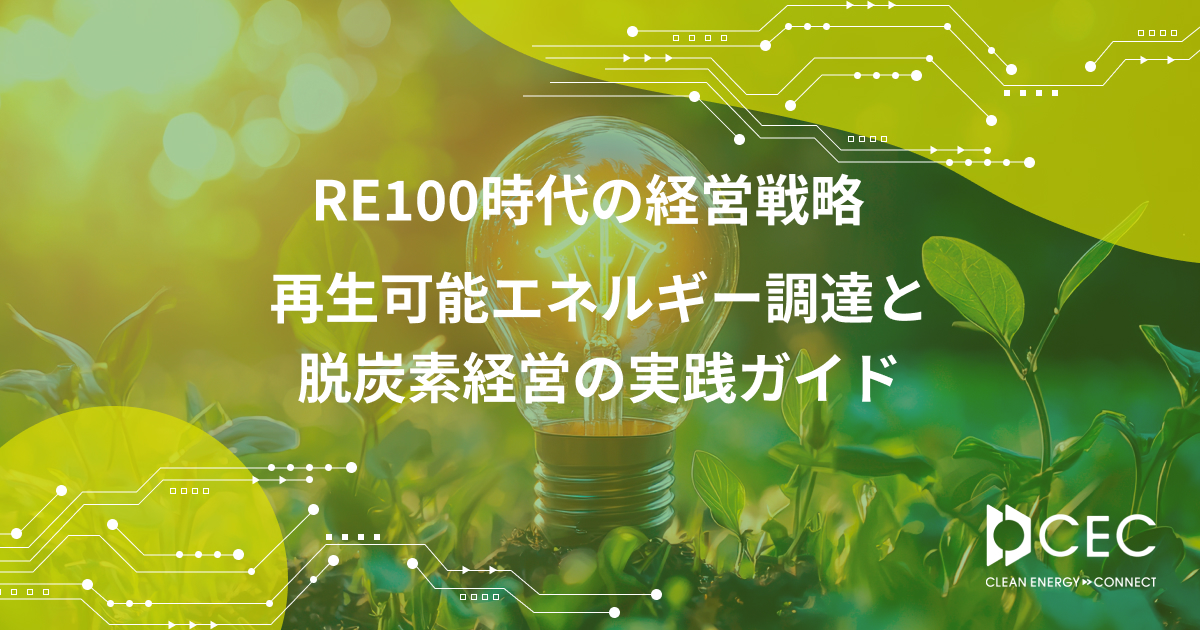
世界的に脱炭素化の動きが加速するなか、企業の間では再生可能エネルギーの活用を広げる取り組みとして「RE100」への加盟が広がっています。
RE100とは、オフィスや工場、店舗など事業活動で使用する電力を、100%再生可能エネルギーに切り替えることを目指す国際的なイニシアティブです。
加盟企業は、再生可能エネルギーの導入を通じて地球温暖化対策に貢献できるだけでなく、サプライチェーン全体に環境への意識を浸透させることができます。
さらに、投資家や顧客からの信頼向上、グローバル市場での競争力強化など、ブランド価値の向上にもつながります。
本コラムでは、RE100の基本的な仕組みや技術要件、最新の市場動向に加え、企業が直面しやすい課題と、その解決に向けた実践的なアクションプランを解説します。
目次
RE100の概要と目的

RE100とは何か?
RE100は、世界の主要企業が事業活動で使用する電力を100%再生可能エネルギーで賄うことを目標とする国際的なイニシアティブです。2014年にNGO「The Climate Group」とCDPが共同で立ち上げ、2024年時点で400社以上が参加しています。日本では(株)リコーが2017年に初めて加盟し、その後多くの大手企業が参画するなど、国内でも広がりを見せています。
国際的な推進プロジェクトとしての意義
パリ協定以降、各国政府が再エネ導入を後押しする政策を展開する中、RE100は企業レベルでの主体的な行動を促す国際的なプラットフォームとして機能しています。企業が再エネ電力を調達することは、単なる環境対応にとどまらず、再エネ証書やコーポレートPPAといった手法を通じて市場に新たな需要を創出し、結果として再生可能エネルギー発電の拡大を加速させる役割を果たしています。
RE100技術要件の詳細解説

企業がRE100を達成するには、単なる宣言にとどまらず、国際的に認められた技術要件を満たす必要があります。
再生可能エネルギーの定義と認証基準
RE100では、再生可能エネルギーの利用を以下の条件で認めています。
- 太陽光、風力、水力、地熱、持続可能なバイオエネルギーといった自然エネルギー由来であること
- GHGプロトコル(スコープ2ガイダンス)に基づき、環境価値証書を用いた調達を排出削減として算定できること
- 環境価値の二重使用を防止すること
このため、各国で認められた環境価値証書(例:日本の非化石証書・Jクレジット、欧州のGO、米国のREC、国際的にはI-RECなど)が活用されます。これらのトラッキングシステムによって調達の透明性と信頼性が担保されます。
【表1:RE100で重視される再エネ電力の技術要件】
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 自然エネルギー由来 | 太陽光、風力、地熱、バイオエネルギー、水力等 |
| 温室効果ガス排出ゼロ | GHGプロトコルに基づく算定 |
| 環境価値の独立性 | 二重使用の禁止とトラッキングによる管理 |
| 第三者認証 | Green-e、I-RECなど国際的認証スキームの利用推奨 |
| 追加性 | 需要家が再生可能エネルギー発電の追加的な拡大に貢献すること |
環境価値の二重使用防止とトラッキングの重要性
再エネ電力の環境価値は証書として発行され、同じ価値が複数の企業により重複して主張されないよう厳格に管理されます。RE100はこのトラッキングの透明性を重視しており、企業は「100%再エネ利用」という主張を第三者に対して説明可能な形で証明することが求められます。
追加性と設備年齢の基準
「追加性」とは、既存設備の延命ではなく、新規発電設備の導入によって実際の温室効果ガス排出削減効果をもたらすことを意味します。RE100自体が一律の「15年ルール」を定めているわけではありませんが、国際的な環境価値証書スキーム(例:Green-e、I-REC Standardなど)では、運転開始から一定期間内(多くは15年以内)の設備を新規性ありとみなす基準が採用されています。これにより、新設や比較的新しい設備からの調達を通じて追加的な排出削減効果が担保されます。
■【新設型】
新規建設された発電設備からの電力・証書を購入。CO₂削減効果が最も明確で推奨度が高い。
■【比較的新しい設備型(設備年齢基準の適用)】
運転開始から15年以内の設備を対象とし、新規性や投資回収を支援。
■【既存支援型】
既に稼働中の設備からの調達。追加効果は限定的だが、再エネ市場の安定化に寄与。
総じて、RE100の達成においては、新設型や比較的新しい設備からの調達が特に重視されます。企業はこれらの基準を踏まえた調達を行うことで、真に追加的な効果を実現できると期待されています。
企業が取り組むべき具体的施策

RE100達成の実現には、戦略的かつ積極的な取り組みが不可欠です。ここでは、企業が取り組むべき主要な施策を整理します。
自社の電力使用状況の把握と現状分析
まずは、各事業拠点における電力使用量、調達方法、再エネ比率を正確に把握することが重要です。エネルギー管理システムを導入し、使用データを継続的に収集・分析することで、改善余地や投資が必要な領域が明確になります。これにより、再エネ導入を急ぐべき拠点や、省エネ・効率化施策の優先順位が把握できます。
再生可能エネルギー電力の調達方法
企業が再エネ電力を調達する手段として、大きく分けて二つの方法があります。
● 自家発電:自社敷地内に太陽光発電設備を自社設備として導入するなど、直接再エネを生み出す方法。
● コーポレートPPA:再エネ発電事業者と長期契約を結び、安定的に再エネ電力を購入する方法。
これらは、地域特性・事業規模・資金調達の状況に応じて選択されます。特にコーポレートPPAは、新規性や契約期間が国際的スキームや第三者検証の基準に適合すれば、RE100への貢献を透明性高く示すことができます。
サプライヤーや政策立案者への働きかけ
企業内の取り組みだけでなく、サプライヤーや地方自治体、政策立案者との協働も欠かせません。再エネ調達の拡大は、自社の利用にとどまらず、市場全体への波及効果をもたらします。具体的には、調達の環境価値を第三者検証に基づいて主張し、証書やトラッキング制度を確実に活用することが求められます。企業が率先してモデルケースを示すことで、同業界や地域全体の取り組みが加速し、カーボンフリーな送電網への移行を支える基盤となります。
RE100達成に向けた市場の動向

国内外企業の動向
国内外の企業は、RE100達成に向けて取り組みを加速しています。例えば、グローバル大手IT企業や製造業、大手不動産会社などは、再エネ電力のコーポレートPPAを活用し、中長期的な取り組みを通じて再生可能エネルギーの利用比率を着実に拡大しています。これらの事例は、企業のブランドイメージ向上やエネルギーコスト管理、さらにはエネルギー価格変動リスクや規制リスクの低減に寄与しており、今後の市場における重要なロールモデルと位置づけられます。
新エネルギー市場と第三者検証制度の活用
電力市場では、再エネ導入を支える新たな仕組みが広がっています。デジタル技術を用いたエネルギートラッキングシステムや、ブロックチェーンによる取引記録の透明化といったソリューションが導入され、再エネ電力の属性情報を正確に管理できるようになっています。これにより、環境価値の二重利用を防ぎ、信頼性の高い取引が可能となります。
加えて、**I-REC(国際再エネ証書)やGreen-e®**といった国際的な第三者認証制度は、企業が自社の再エネ利用実績を外部に対して証明するうえで有効な仕組みです。これらの認証を取得することで、投資家・顧客・取引先に対して透明性と信頼性を確保できるため、多くの企業が積極的に活用を進めています。
まとめ:持続可能な未来へのアクションプランと今後の展望

企業がRE100の目標達成に取り組む際、重要なのは以下のポイントです。
① 自社のエネルギー使用状況を正確に把握する。
② 技術要件に沿った調達手段(自家発電・コーポレートPPA等)を選択する。
③ 第三者検証やデジタルツールを活用し、透明性を担保する。
④ サプライヤーや政策立案者と連携し、市場全体で普及を促進する。
これらは単なるコスト最適化ではなく、脱炭素化を通じた 企業価値の向上、リスク回避、そして競争優位の確立 に直結します。再エネ技術の進化や市場制度の変革は、新たな課題と同時に企業に大きな成長機会をもたらしています。戦略的な再エネ導入は、CSRの枠を超え、長期的な事業継続性や投資家・顧客からの信頼確保に直結する経営判断といえます。
今後、世界各国でカーボンフリー電力システムへの転換が加速する中、日本企業には自ら行動を起こし、市場をリードする姿勢が求められます。RE100の基準に沿った取り組みを実行することで、企業はグローバルな気候変動対策の先駆者としての地位を確立し、社会全体に持続可能な未来を示す存在となるでしょう。






